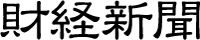関連記事
慶大、潰瘍性大腸炎における遺伝子変異の蓄積を発見、がんの機構解明に光
人の大腸上皮は加齢とともに遺伝子変異が蓄積することで、大腸がんの原因となることがこれまでの研究で明らかになっている。一方で腸内環境の変化と大腸上皮の遺伝子変異の蓄積との関係は、これまで不明であり、特に慢性炎症などの腸内環境の変化は大腸がんのリスクが示唆されてきた。そんな中で慶應義塾大学医学部の研究グループは19日、潰瘍性大腸炎患者の大腸組織に、特定の遺伝子変異が蓄積していることを発見したと発表した。
【こちらも】大腸がんや乳がんの「がん幹細胞」、制御機構を解明 治療法に期待 藤田医科大など
本研究の成果は18日付のNature誌のオンライン版に掲載されている。
慶應義塾大学の研究グループは、以前から「オルガノイド培養技術」を応用することで大腸の幹細胞の解析を行っており、正常な大腸上皮幹細胞において、年齢に比例して遺伝子変異が蓄積することを発見するなどの成果をあげてきた。遺伝子変異の蓄積には個人差があることも示唆されていた。
今回研究グループが着目したのは、この遺伝子変異蓄積の個人差と腸内環境の関係である。健常者と潰瘍性大腸炎の患者において、大腸組織細胞の体外培養を行うことでそれぞれの遺伝子変異発生の仕方を比較した。
その結果、潰瘍性大腸炎の患者の細胞には、より多くの遺伝子変異が検出された。ただしその遺伝子変異の多くは、大腸がんの際に見られるものでは、なくむしろ慢性炎症に関連した遺伝子変異であることも判明。さらにその遺伝子変異は、炎症環境の中で生存しやすくなるものであり、腸内環境の変化に適応するための変異であることも判明している。
これらの遺伝子変異が生じた大腸上皮細胞が蓄積していくことによる影響は、まだ未解明である。炎症によって遺伝子変異の蓄積に影響が出ることが、がんの原因であるという仮説については、これまでも予想されてきた。しかし技術的な限界によって、現在まで解明は困難とされてきた。今回の研究成果を受けて、潰瘍性大腸炎の病態や大腸がんの発生にどのように関与しているかについては、今後の研究による解明が期待される。
スポンサードリンク