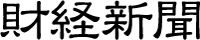関連記事
日産が仏ルノーとの持株調整問題に合意して生じた、「明」と懸念 (上)

(c) 123rf[写真拡大]
1月30日、日産とルノーは「両社の協議が重要なマイルストーン(節目)を迎えた」と声明を出した。難航していた持株の調整問題に、ようやく合意が成立したためだ。
【こちらも】日産とルノー、出資比率見直し 相互15%と声明 EV専門会社設立
日産は重大な経営危機に直面していた1999年、ルノーから37%の出資を受けて危機を脱した。言うなれば「命の恩人」のような大切な存在だったが、日産の業況が回復してくると規模的にはルノーを凌駕する自動車メーカーとしてのプライドが、頭をもたげて来た。
もちろん過去の経緯を考えると、表立って口にすることは憚られたが、進駐軍のように日産に乗り込んで来たルノーの職員に顎で使われるような立場に置かれた現場では、鬱憤がマグマのように膨らんだ部署もあったようだ。
日産の社内に静かに蔓延していたその不満が表面化したのは、フランス政府に主導されたかのように、19年にルノーが持ち出した経営統合問題だ。その時点でルノーが保有する日産の株式が、43%と過半数も視野に入る規模に達していたことや、フランスの法律の制限で日産が保有する15%のルノー株には議決権がないことへの疑問が論じられていた。そのため、対等な関係を模索する動きが強まったものの、デリケートな問題であるため表立って交渉する糸口が見出せない状況が続いた。
そんな時に自動車業界に訪れたEV化の波が、ルノーの心変わりのキッカケになった。EV化の荒波を乗り越えて生き残るために、大胆な業態の変更を決断したルノーは、必要となる巨額な資金の一部に充当するため、日産の保有株式を現金化する発想に至ったのだ。
今回の持株調整問題は、日産の潜在的な期待に応えているように見えても、実質的にはルノーの資金繰りとしての性格が強い。協力を求められる立場に立った日産は、協業の過程で生まれた特許権という共有財産を利用する際に、日産の了解が必要だとする条件を付けて、ルノーに飲ませた。
もし日産が持株の調整を主導しようとしたら、こんな形で合意が成立することはなかっただろう。言うなれば、自動車業界を飲み込むEV化の荒波には、日産とルノーの持株問題を解決する神通力のような働きがあったことになる。長年日産の関係者が望んでいた、対等の関係になるという夢が実現することは、日産にとって「明」であろう(続く)。(記事:矢牧滋夫・記事一覧を見る)
スポンサードリンク