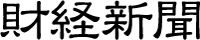関連記事
中性子星同士の連星が作られる過程を初めて発見 国立天文台など

「超新星 iPTF14gqr の出現前と出現後の画像。破線の丸で囲まれた部分が超新星。」(c)SDSS/Caltech[写真拡大]
2017年、LIGO(レーザー干渉計重力波観測所)などにより、「アインシュタイン博士の最後の宿題」と言われた重力波検出が観測された。特に、中性子星同士の合体の検出は、多くの科学者たちの念願であり、その観察が1年前にあったことが思い出される。ところが、中性子星同士の連星というのは、2つの超新星爆発(以後、超新星)を起こした星同士の連星であり、それが出来る条件はとても難しく、形成過程もよくわかっていなかった。
【こちらも】中性子星同士の衝突が史上初めて観測される
そこで国立天文台理論研究部の守屋尭(もりやたかし)特任助教らの研究チームは、中性子星同士の連星がどのように生まれるのか、理論を組み立てた。そして今回、過去の観測データから、その説と一致する連星を世界で初めて発見した。
通常の超新星が連星2つで同じように起きた場合、バランスが崩れてしまい、中性子星同士の連星は作られないという。では、どのようにして連星中性子星は作られるのか。守屋助教らの研究チームが立てた理論は、先に超新星が起きて中性子星になった星の重力などにより、残り一方の恒星は、水素やヘリウムで出来た外層部分が、ほとんど剥がれ落ちた状態になり、その状態のまま超新星を起こすだろうという説であった。後に起きる超新星の規模は、通常の超新星の10分の1になるだろう、と計算された。またその超新星の場合、爆発後急激に冷えて減光し、再び5日から10日後の間に、最も明るくなることなどについても予測されていた。
そして、このシミュレーションで予測した天体と一致する超新星が、パロマー突発天体観測プロジェクト(intermediate Palomar Transient Factory : iPTF)の観測データから発見され、理論は証明された。
スローン・デジタル・スカイサーベイ(SDSS)と呼ばれる、米、日本、独を中心に始まり、現在、全世界25カ所の研究機関で運用されている共同プロジェクトがある。2014年10月19日に「超新星 iPTF14gqr 」という超新星が発見されていた。
この超新星が、今回の中性子星同士の連星の理論通り、通常の超新星よりも爆発エネルギーが小さく、爆発時に放出された物質がきわめて少なかった。理論の1つである、超新星の直前に希薄な広がったヘリウムの層を周りに形成する、という守屋助教の指摘通り、この天体の周囲には希薄なヘリウムの層が広がっていることもわかった。
この研究の予測計算には、国立天文台で稼働しているCray XC30のスーパーコンピューター「アテルイ」が用いられた。
今回の研究は、2018年10月12日付の米国の科学雑誌『サイエンス』に掲載された。
スポンサードリンク
関連キーワード