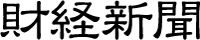関連記事
【ホンダ・S2000衰えぬ人気】ピュアスポーツの魅力は高回転型エンジンから始まる

ホンダ・S2000 TYPE S (写真: 本田技研工業の発表資料より)[写真拡大]
ホンダ・S2000の復活を望む声は収まらないようだ。最近、スポーツセダンを始め、スポーツバージョンを設ける動きが目立っている。そんな中でマツダ・ロードスターなど、ライトウエイト・スポーツの存在を忘れるわけにはいくまい。
【こちらも】【ホンダ・ベビーNSX?】S2000後継?伝統のライトウエイトスポーツ?新時代
EV車の0-100km加速性能は、セダンであっても本格的スポーツカーを凌ぐ場合もある。それは電動モーターの特性で、最初の1回転から最大トルクを得ることが出来るのが大きい。強烈な加速をアクセルを踏むだけで得られる。特別なテクニックは必要なく、誰もが均一な加速性能を得られる。とても手軽な加速性能だ。
ホンダ・S2000は2.0L直列4気筒DOHC自然吸気エンジン、最高出力250ps/8300rpm、最大トルク22.2kgm/7500rpm、レッドゾーン(最大許容回転数)9000rpmと、現在では考えられないF1用エンジンかと思わせる高回転型エンジンで登場した。現在ではタコメーターはあれども、レッドゾーンを意識したこともない人も多いことだろう。
このエンジンの最大の特徴は「高回転域で最高の性能を発揮する」こと、自然吸気エンジンでアクセル操作に極めて敏感に反応することだ。ターボチャージャーを使わないので低速域でのトルクはないが、高回転に保てば素晴らしい反応を見せる。回転が上がるときも、下がるときも敏感に反応するのだ。これが大事なことで、「ドライバーの操作に対して忠実に反応する」ことになる。
ターボエンジンでは立ち上がりの反応がどうしても鈍くなり、逆にEVでは高回転の伸びがない。そこでドライバーはどんな時でもエンジンを高回転域にとどめて、どんな場面からでも即座に反応するテクニックを追い求めることになる。
ワインディングロードを走るとき、カーブに差しかかったのならブレーキを踏み速度を落とさねばならない。その時、ギアがトップのままであるとエンジン回転は落ちていく。きついカーブで速度を落とせば落とすほど、エンジン回転は落ちる。そのままではカーブの出口で加速しようとすると、エンジン回転が落ちており、有効なトルクがない。もたもたと立ち上がれない状態になってしまう。
そこでギアを落とし、有効なトルクが発生している回転数の範囲にエンジンを回し続けることが大切だ。トップから5速、4速、3速、2速など必要なギアを選ぶ。しかし、6速、5速、4速と3速が離れた減速比だと、ある程度速度が落ちるまで待たねばレッドゾーンに入ってしまう。そこで6-5-4-3速などは接近したギア比にして、速度が落ちたなら即座にシフトダウンを行ってエンジン回転を有効なトルクの発生している回転に保っていく。これがスポーツカーの性能のなだ。
ライトウエイトスポーツカーを駆る楽しみは、ドライバーとしてはこの「ギアシフト」に集約される。そのため、ギアシフトレバーのフィーリングは重要で、ぺタル配置もヒール・アンド・トウのやりやすいことが必要だ。つまり、MTギアを素早くシフトするにはシンクロナイザーの働きも重要だが、それを必要としないほど、車速とエンジン回転を各ギア比ごとに合わせることが大切だ。
免許取りたての頃、エンジン回転と車速を各ギアごとに合わせる感を養うため、クラッチを切らずにシフトする練習を繰り返した。アクセルで車速とうまく合わせられないと「ギャッ」と「ギア鳴り」を起こす。それだけでなくギアが欠けてしまうこともある。シフトレバーが全く抵抗感なく収まった時の快感が忘れられない。
それをコーナーでのブレーキングと同時に行えるように、右足だけでヒール・アンド・トウ使うのだ。つまり足裏のトウでブレーキを踏み、ヒールでアクセルを調整して、回転を合わせるのだ。ダブルクラッチとはその時、ミッションがニュートラルの状態で一度クラッチを繋ぎ、シフトダウンするギアの回転を上げ、車速に合わせて再びクラッチを踏み、シフトレバーを動かすのだ。上手になるとシンクロナイザーなど必要とせず、ギアチェンジが出来るようになる。
この動作を素早くすることで、エンジンのトルクが切られている時間を出来るだけ短くする効果がある。現在のCVTやDCT、ATなどのドライビングでは考えれれないほど忙しいのだ。その忙しさを求めて、高回転型エンジンとクロスレシオMTが必要なのだ。それが、ホンダ・S2000にはある。スポーツカー好きとはこのようなもので、EVの1ぺタルで調整すれば済むようになった車があっても、わざわざこの快感を求め続けているのである。(記事:kenzoogata・記事一覧を見る)
スポンサードリンク