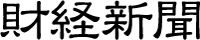関連記事
都心不動産価格に異変? コロナ禍に追い打ちをかける「生産緑地制度の2022年問題」 後編
「生産緑地制度の2022年問題」とは、生産緑地制度の期限である2022年に、都内の農地が宅地として売り出されることをきっかけに、土地の供給が一気に増え、不動産価格が暴落する可能性について指摘されたものだ。
【前回は】都心不動産価格に異変? コロナ禍に追い打ちをかける「生産緑地制度の2022年問題」 前編
まず、生産緑地制度の歴史を振り返ると、1972年に定められた生産緑地法に遡る。高度経済成長期によって都内の緑地が宅地に転用されていった結果、緑地が失われ、住環境が悪化、さらに土地の地盤保持機能や保水機能を失っていったため、土地不足や地価高騰の抑制を目的として設けられたのがこの法律だ。
しかし、その後も農地や緑地の宅地化が止まらなかったため、1992年の生産緑地法改正によって、市街化区域内の農地が、生産緑地と宅地化農地に区別されるようになった。ここで指定された生産緑地については、様々な税優遇を受けられる一方で、一定期間は農地として管理・維持をするという条件が付されたわけだ。
この一定期間というのが30年間であり、1992年から30年後である2022年に、その期間終えることになる。そして、生産緑地の多くは東京である。過去のデータでは、東京に約3,300ヘクタール、神奈川と埼玉、千葉を加えると約8,000ヘクタールにもなる。1ヘクタールはおよそ3030坪であるから、都内や都内近郊にこれだけの土地が供給されると考えれば、少子高齢化である現代において、その反動は計り知れないものとなるだろう。
しかしながら、2022年を迎えた途端に全ての生産緑地が宅地として供給されるわけではない。まずは、この制度の税優遇措置が10年間にわたって延長される特例が設けられることになった。この特例により、生産緑地の8割程度が延長を申請したということだ。
もちろん、この特例が無かったとしても、生産緑地として維持することはできた。そもそも農地として管理されてきたということは、大半が農業を営んできたことになる。維持ができなくなるということは、生産量地の所有者が高齢になり、後継者もおらず、農家を廃業する場合などに限られるのだ。そのほかに、貸付制度もある。
とはいえども、仮に8,000ヘクタールの1割程度が宅地化され、売却されるとしても、それなりのインパクトにはなるだろう。800ヘクタールで約240万坪である。都内であっても、約100万坪が宅地になればどうだろうか。
コロナ禍によって都心部に住む必要が無くなり、自然の多い郊外に住む、もしくはより都心部の高級マンションに住むという選択肢以外に、都心に近い郊外、かつ住環境が良い場所に広い敷地をもった戸建を購入するという選択肢を与えることにならないだろうか。2022年以降の不動産価格には、十分に注視されたい。(記事:小林弘卓・記事一覧を見る)
スポンサードリンク