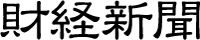関連記事
日経平均株価30,714円は超えられない? 岸田政権を待ち受ける前途多難 後編
アメリカのFRBはコロナショックの直後、リーマンショック時の金融緩和をも凌駕する大規模な金融緩和を断行したが、政府の巨額な財政出動との相乗効果もあり、結果として、株式市場は見事なV字回復を遂げている。
【前回は】日経平均株価30,714円は超えられない? 岸田政権を待ち受ける前途多難 前編
しかしながら、大規模な金融緩和はあくまでもカンフル剤でしかなく、打ち続けるわけにはいかない。過剰な緩和によって懸念されるのは過度なインフレ(物価上昇)などの副作用であり、その抑制のために、中央銀行は利上げをして金融引き締めることになる。
金融引き締めは資金の流動性を弱めるため、株式市場にとっては大きなネガティブ要素となることは避けられない。かつてのバーナンキショックのように、テーパリングの示唆だけで株価が暴落するほど市場はセンシティブなのである。そして、アメリカの株式市場が金融引き締めによって下落すれば、相関性の高い日本の株式市場も連動して下落することは免れないだろう。
とはいえども、中央銀行の金融政策は物価の安定が主たる目的である。金融緩和と金融引き締めをバランス良く行い、物価の急上昇や下落をコントロールすることで、国民の生活を守る役務を担っており、金融政策は株価の維持が目的ではない。
もっとも、中央銀行は様々な経済指標で経済の動向を確認しており、株式市場がテーパリングに耐えうることを確認したうえでの金融政策の転換ではある。将来的に経済の成長を見込むことができれば下落は一時的であり、株価は再上昇するだろう。だがワクチン接種率が伸び悩み、感染者数が急増しているアメリカ国内の状況を見ると、その前途に一抹の不安も残る。
さらに、中国の不動産大手である恒大集団(エバーグランデ)の経営破綻問題により、不動産バブルの懸念が注目を集めている。中国政府は不動産バブルに歯止めをかけようと、不動産税の試験的導入を実施するが、さじ加減を間違えればバブル崩壊の助長にもつながる。日本のバブル崩壊がその悪しき前例であるが、万が一、中国で不動産バブルが崩壊するとなれば、金融不安がパンデミックし、新たな金融ショックを引き起こしかねない。
アメリカを始めとする各国の中央銀行のテーパリングが差し迫り、中国の金融不安が見え隠れするなかで、原油の高騰と円安がさらに追い打ちをかける。少子高齢化などの社会問題に、脱炭素化やデジタル化遅れも大きな課題だが、果たして岸田政権はこれらすべての懸念や課題を払しょくできるような成長戦略を描けるだろうか。もはや、限られた時間は少ないのである。
日本の株式市場における直近の投資主体別売買状況を確認すると、菅前首相の退陣表明からの株価急上昇と岸田ショック、そして選挙中の上昇に関しては、そのほとんどが海外投資家の売買動向に左右されていることがわかる。つまりは、海外投資家に投資をしたいと思わせるような成長戦略を描けなければ、日本の株式市場は自律反発に乏しいまま、中長期的に緩やかな下落を続けていくだろう。
9月14日につけた日経平均株価のバブル後最高値、30,714円が当面の語り草となってしまうのだろうか。海外市場の動向に注視しながら、岸田政権の成長戦略に注目されたい。(記事:小林弘卓・記事一覧を見る)
スポンサードリンク