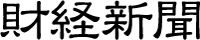関連記事
認知症を予防する腸内細菌を発見 名大らの研究
名古屋大学らの研究グループは、認知症の発症抑制に関わる腸内細菌を発見したと発表した。腸内細菌と認知症に関連性があるようだという研究結果は、これまでにもみられていたが、今回の発見により、新しい認知症治療法や予防法が開発されていくことが期待される。
【こちらも】老化による腸内細菌の変化メカニズム、世界で初めて解明 北大の研究
今回の研究は、名古屋大学大学院の平山正昭准教授(医学系研究科オミックス医療科学)や、大野欽司教授(神経遺伝情報学)らの研究グループが、岡山能神経内科クリニックの柏原健一院長や、岩手医科大学の前田哲也教授(神経内科老年科学)らと共同で行ったもの。その成果は、9日の「npj Parkinson's Disease」オンライン版に掲載された。
認知症は高齢化社会である日本において、重要な課題である。2025年には65歳以上の5人に1人が認知症を発症すると予測されている。認知症の中でも患者が多いのが、アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、血管性認知症である。
今回研究対象とされたのは、認知症の中でも2番目に多い「レビー小体型認知症」である。この認知症の特徴は、幻覚が起こることや、症状が進むとパーキンソン症状が起こってくること(不随意運動が起こること)である。現状は、アルツハイマー型認知症と同じく、進行を抑える薬による治療のみで、根本的な治療法はまだ存在しない。
レビー小体型認知症では、脳にαシヌクレインというタンパク質が蓄積していることが知られている。同じくαシヌクレインが脳に蓄積する類似の疾患として、パーキンソン病や、レム睡眠行動異常症がある。
今回研究グループは、パーキンソン病の患者224人、レビー小体型認知症患者26人、レム睡眠行動異常症28人、健常者147人の便に含まれる、細菌と胆汁酸などの代謝物について調べた。
その結果、健常者と比べて、レビー小体型認知症とパーキンソン病の患者では、短鎖脂肪酸を増やすタイプの腸内細菌が減り、腸の粘膜を分解する細菌が増えていることがわかった。短鎖脂肪酸は、体内でエネルギーとして使われたり、腸内環境を酸性にして病原菌の増殖を抑えたり、腸を刺激して動きを促進するなど、様々な機能が知られている。一方で、レビー小体型認知症でのみ増加し、パーキンソン病では増加しない腸内細菌も明らかになった。
研究グループがこれらの結果を解析した結果、健常者と比較してレビー小体型認知症で減少していたのは全て、短鎖脂肪酸産生菌だった。このことは、アルツハイマー病やALSなどの神経変性疾患で共通してみられる現象である。短鎖脂肪酸が神経炎症を抑えたり、免疫反応を制御するT細胞を増加させる働きを持つことに関連していると考えられる。
また胆汁酸産生菌の増加は、レビー小体型認知症でのみでみられ、パーキンソン病ではみられなかった。そのため胆汁酸産生菌が産生する胆汁酸の働きが、レビー小体型認知症におけるパーキンソン症状の出現を遅らせていると考えられる。さらにビフィズス菌はアルツハイマー病、レビー小体認知症で共通して減少しており、ビフィズス菌の減少は認知症状の悪化と関連していると考えられた。
これまでも腸内細菌と認知症の間には関連性があることは予測されていたが、それは細菌による認知症への負の影響に関するものが主であった。今回、病気の進行を遅らせる可能性のある腸内細菌が明らかになったことは、大きな成果と考えられる。
腸内細菌については、まだ多くの不明点や課題が残る分野でもある。今後、新しい認知症の治療法や予防法として応用されていくことが期待される。(記事:室園美映子・記事一覧を見る)
スポンサードリンク