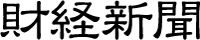関連記事
「円の闘い」(4) 1ドル・360円と日本経済
GHQ司令で決まった「1ドル・360円」にはその後「レートを維持するために、円買い・ドル売りが何度となく繰り返された。結果、外貨準備(保有ドル)が底をつき金融引き締めを余儀なくされる場面が多々あった」とする「円高だった」とする論と、「戦後の経済復興・高成長を牽引したのは、1ドル・360円下の輸出であることは否定しがたい事実」とする「有利な為替レート(円安)」が交錯して論じられた。
浅学菲才な私は「どっちの論が的を射ているのか」という判断に迷った。取材を繰り返した。そんななかで日銀理事から当時の山一証券経済研究所理事長に転じた直後の故吉野俊彦に出会った。吉野は私の問いかけにこう応じた。「輸出の拡大で増えたドルは、成長の元手となる輸入に振り向けられた。当然、国際収支は赤字になる。そうなると金融を引き締め景気拡大に歯止めをかけ輸入減の策を執った。国際収支の均衡が取り戻せるのを待ち、再び金融を緩め輸入増・輸出増に向かった。その愚直なまでの繰り返しが戦後の日本経済の奇跡ともいえる高度成長を実現した。愚直さが幸いした」。そして一呼吸入れ、こう断じた。「つまりはインフレが起こる前段階で引き締め策が打たれ、日本経済の高度成長を水膨れではない筋肉質のものにしたといえる」。吉野の論を時の経過と摺り合わしてみた。納得がいった。以来「GHQ司令による有効なドル安を軸に、巧みな金融政策で日本の高度成長は実現された」が、私の見方になった。
しかしそうした好循環も、徐々に変化を余儀なくされた。1960年代も終盤に差し掛かったころである。米国の疲弊が日増しに顕著になっていった。米国は戦後の東西対立の激化の中で西側諸国の盟主として、自国の巨大市場を西側諸国に開放した。最恵国待遇を供与し、輸出の拡充・国力増強を促した。大量にドルを印刷し世界に向けてばらまいたのである。こうした状況下で米国は東西対立への対峙策として、ベトナム戦争(1960年~)という泥沼に身を投じる結果となった。軍事費の膨張は米国造幣局の輪転機をフル回転に追い込んだ。
ドルを基軸とした西側経済は、インフレの渦中にいやおうなく追い込まれていった。が、「有利な円安」状態に身を置いていた日本にとっては、輸出を一段と加速させる事態に繋がった。68年には30億ドルに一気に近づいた外貨準備高は、70年には40億ドルを超えるに至った。こうなると先の吉野の「好循環」も通用しなくなってしまった。
そうした中、元日銀理事で日本開発銀行副総裁だった故緒方四十郎を取材する機会をえた。緒方は時流を「筋肉質な高度成長の過程で日本は、想像以上の国際競争力を身につけた。インフレ進行の中で日本は、独り勝ちの様相となった。外貨準備高は輸入増加策を嘲笑うかのように増え続け、国際収支は黒字幅を拡げていった。激変に政府・日銀は混乱した。(69年9月1日)日銀は公定歩合を5.8%から6.25%に引き上げた。過去に例をみない引き上げ幅だった。インフレ退治を狙った金融引き締め策だった。国内景気の過熱感の鎮静には効果があった。がその分輸入額が落ち、皮肉にも外貨準備は増え続け国際収支の黒字幅は増加した」と説明してくれた。
そして「これは書くなよ」という条件で次の様な台詞も口にした。緒方さん、遠からず私もそちらに参りますのでお許しをと手前勝手に約束を破り記す。「このあたりから1ドル・360円に安閑として経済大国になった日本に対し“睨むべき日本”“異質国日本”が芽生えていたといえる。同じ敗戦国でありかつ戦後の経済成長で日本と双璧だった西ドイツは、69年10月に、マルクを10%近く切り上げる措置を執っていたからなおさらだった」。
そして輸出大国・日本の最大の拠り所だった1ドル・360円が崩落の時を迎えるベルが鳴ったのは、世界第2位の経済大国となった僅か3年目の71年8月15日午前9時(日本時間8月16日午前10時)だった。(敬称、略)(記事:千葉明・記事一覧を見る)
スポンサードリンク