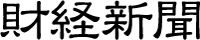関連記事
人工頭脳(AI)時代に人間翻訳は生き残れるか?:第四回 HAL 9000 は蘇ったか?
先日、一時の余暇を楽しもうとDVDのコレクションから一枚をランダムに取り出しトレイに載せた。「2001: Space Odyssey」(和名「2001年宇宙の旅」)、70年代のSF映画だ。懐かしい一本だ。筋はやや朦朧としていたが、まだDGのなかったころの宇宙もの、流石にトリックが面白く感心しつつ見続ける。ほどなく、ご存知、HAL9000の登場。はしなくもAIばなしの原点を目の前に、筆者は宇宙のどうのはそっちに退けて、あの「赤いランプ」の振る舞いを注視することになった。
誤作動を理由に解体され、呻きながら消されていく断末魔のHAL9000を眺めながら、筆者はふっと思った:「いま巷を賑わしているAI人工頭脳は、こうして自分の過ちを「認識」し「修正」を誓いながら抹殺されたこのHAL9000の化身ではないか?半世紀後に出現したAlphaGoはその分身で、すでに囲碁の世界で人知に復讐し終え、GNMT実装のGoggle 翻訳もほかの分身で、まさに人間翻訳に挑んでいるという図式ではないか?」
■「古池や……」
本題へ入る前に、お耳に入れておきたい話しがある。ある古老が語る般若心経ばなしに、こんな下りがあった。唐の玄奘三蔵が仏典をサンスクリットから漢訳したとき、翻訳不能の部分を原語の音訳で残しながら、「翻訳は原語への反逆なり」と喝破した、と。その古老はさらに、「古池や….の芭蕉の名句が翻訳できるものか」と問いかけるのだ。一面の古池があって一匹の蛙が飛び込んだ、だけのことではなかろう、と問い詰めるのだ。「それでは俳聖芭蕉の心は生きまい」、と。身勝手な翻訳は原句への反逆では、と。この辺りの呼吸は、長年翻訳を生業にしてきた筆者にはしみじみ伝わるのだ。
前回の揚げ雲雀ではないが、詩句はいざ知らず詩心を「訳す」には、文化への豊かな感性と只ならぬ覚悟がなければできないとしたものだ。古池をa pondとも思わず、蛙もa frogとばかりとは思えぬ感性が共有されておらねば、芭蕉は「英語」にはならぬ。つまりは、翻訳とは言葉のすげ替えではなく、文化的感性の紡ぎ合いでは、という問いかけだ。
「古池や….」をAIが訳せば、池があって蛙が飛び込んだ、でいい。人間ではそうはいかない。とく日本人ならば、一捻り入れねばならぬ。入れて、芭蕉の詩心、いや句心を滲ませねばならぬ。池と蛙を詠み込んで捻れればいいが、池と蛙なしの方が蕉風を訳出できる、などということにもなりかねない。データをdeep-learningしてこそのAI翻訳では、古池と蛙がいなければデータ不足で仕事にならない。侘び寂びが文化なら、AI翻訳の手には負えないことになる。
では、今回のテーマに入ろう。
■二刀の芸
翻訳は言葉でなく文化の紡ぎ合いだ、というのは筆者の持論だ。翻訳を機織りに喩えれば、縦横の糸をそれぞれの言葉を裏打ちする文化と捉えて、染めと織りの技術を研ぎ澄まして織りあげるのだ。縦の糸は原書の言葉、横の糸は訳出する言葉、いずれの糸も同じような感度と精度で扱わねばならない。翻訳とはそういった作業だ。二本の糸を操る、つまり二刀の芸だ。長年のアメリカ生活と現職時代の言語環境から、筆者は無意識に言葉の両天秤に慣れ、二つの言葉は常に同じ比重で扱ってきたことで、いつかな巧まずに「二刀流」感覚が育った。
宮本武蔵の二天一流、世にいう二刀流は講談の華だ。いまなら野球の大谷祥平が、投打を使い分けていま巷を沸かしている。武蔵が二刀を垂らせば、いずれも手練れの剣だ。祥平に投げさせれば160キロの剛球が冴え、バットを構えれば投手とは思えぬスラッガーに変身する。いずれも左右、劣らぬ技あればこその至芸だ。
言うまでもなく、二刀とは二つの言語であり、実地の翻訳では一方が母国語で他方は外国語になる。願わくんば、ともに不自由なく駆使できるレベルにあることだが、常識的には母国語が流暢で、他国語の技倆や如何に、というところだ。
世の翻訳物を一瞥すると、日本の場合圧倒的に英和が多いようだ。流暢な筈の母国語に訳し込む方が安易だからにせよ、これを予想できるにせよ当然な現象だとは思いたくない。この現象は、架かって翻訳家の資質と態度にあるからで、大方が翻訳という作業の本質を知りつつ顧みない怠惰が原因であることを猛省すべきだ。日本の豊かな文化が世界へ充分発信されずに埋もれているのは見るに忍びない。心ある翻訳家が、英語を一片の言葉とだけ捉えず、その背後の文化ともどもに取り込み織り上げて、あたかも「英語織」の着物を纏う境地に達することができれば、わが日本の豊かな文化が混迷する世界に滔々と流布するはずだ。
■大まじめ
言葉が文化だという話しの例を、いくつかお話ししたい。学校ではまず教えまいと言う下世話な言葉の響きが、翻訳の現場では活性を産むことがある。
こんな例は如何だろう。「やっこさん、なんかおおまじめだったぜ。」、などという科白はよく聞くが、こんなときに英語圏では、少なくともアメリカではどう言い回すか、ご存知だろうか?「You know what? He was dead serious about that….」日本人には思いもよらぬところだ。
ドイツでは「よく眠る」喩えにウサギを引き合いに出すというが、日本なら左甚五郎ならぬ「眠り猫」だろう。豚に真珠などといっても、猫に小判を聞き慣れている日本人にはいまいちだ。これは言葉だけではない、立ち居振る舞いから人付き合いまで、言葉ごとに、いや国柄に顕れ文化に顕れ、言葉に顕れて翻訳を悩ませるという順序だ。
■シラミと櫛
何ごとも「とことんやる」となれば、日本人なら「シラミつぶし」にやるが、これなども先方では「シラミ」は発想しない。その「発想しない」ところが文化で、それは共有しないとことには手も足もでない。英語ではシラミでなく櫛を連想する。細かい櫛の刻みで掬うことから comb throughという動詞を発想するわけだ。
言葉の詮索はほどほどにしよう。筆者のメッセージはこうだ。どちらの文化がどうだ、ということでなく、そんな二枚の着物を着分けることから本物の翻訳が生まれるものだ、と。翻訳の現場では、それが言葉に留まらず大きな網を被せたような質感のある発想の違いになって顕れる、と。身につける着物も、一重では叶わず十二単(ひとえ)にもなろうというものなのだ。AIに十二単が纏えるか、という話しだ。
そんな芸はAIにはあるまいと言いたいのか、との早とちりは迷惑至極。その命題はエピローグに譲って、次回はこの二刀の芸を、AIを迎え撃つ「二刀流翻訳術」として、その奥義を明かして見たい。
スポンサードリンク
関連キーワード