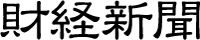関連記事
戦国時代から続く「向こう傷は問わない」という組織論
戦国時代の名軍師・山本勘助は、武田家中において、トップの信玄から末端の一兵卒にいたるまで、絶大な信頼を勝ち得ることが出来ていたという。その理由は、何よりも「上田原の戦い」や「戸石崩れ」などの戦場において、窮地に陥った武田軍を絶妙な機知と働きにより態勢を立て直し、危機を脱することに成功した功績に他ならない。
戦国時代の大名家においては、戦場での活躍こそ、家中での発言権を得られる最低条件であり、武士としての本分を立派に果たせてこそ、一人前の存在として認められていた。つまり、武士である以上戦場で手柄を立ててこそ存在意義があり、逆に幾ら弁が立っても、それが机上論であったり土壇場で逃げ腰だったりすると、人として信用してもらえないという厳しい現実があった。
現代でも「向こう傷は問わない」という諺が、時折、組織論などで用いられることがある。
例えばバブル経済の時代には、やり手の銀行マンが売上増に功を焦るあまり、与信管理よりも目先の貸付の拡大に賭けた結果、その取引先が突然に倒産して不良債権を掴まされたりした場合などに、この言葉が用いられた。
それは、そうした"イケイケドンドン"の社風の会社であれば、仮に本日100万円の損失を蒙ったとしても、さらに仕事に精を出し明日200万円を儲ければ、今日の損失はマイナスに評価しないという人事考課の基準を説明する際に用いられることが多い。
つまり、戦場で同じ傷を負ったにせよ、敵と向かい合って、真正面に傷つけられた傷は、前向きな姿勢の現れであると好意に評価し、逆に、背中を斬られたりすれば敵に背を向けて逃げようとしたところを斬られたものと、ネガティブに見なされるということだ。武田家中においても、戦場での働きが充分でなければ、決して誰も勘助のことを尊敬に値する武将としては認めなかったことだろう。
つまり、現代のビジネス社会においても、組織の中で認めてもらいたかったら、自分に与えられた使命を「向う傷」を追っても十二分にこなせたなら、そこでようやく評価され、自分の意見を述べる資格が与えられるものと知るべきなのである。(記事:マーヴェリック・記事一覧を見る)
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 5年先まで使える広告代理店的プレゼンテーション術 (79)
 2/10 09:42
2/10 09:42 - 5年先まで使える広告代理店的プレゼンテーション術 (78)
 12/ 9 09:40
12/ 9 09:40 - 5年先まで使える広告代理店的プレゼンテーション術 (77)
 7/14 16:18
7/14 16:18 - 5年先まで使える広告代理店的プレゼンテーション術 (76)
 5/ 8 15:49
5/ 8 15:49 - 5年先まで使える広告代理店的プレゼンテーション術 (75)
 3/ 3 15:46
3/ 3 15:46