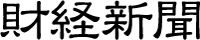関連記事
「円の闘い」(1) “円”の誕生
今回から数回にわたり、「1ドル・100円台」に至る円の足跡を辿ってみたい。振り返ってみて、そこには「闘いの痕跡」「翻弄の苦渋」があったことを痛感した。
1回目は、そもそも日本の基軸通貨が「円」と決まった経緯である。1871年(明治4年)5月10日、明治政府は「新貨条例」を交付した。条例には「新貨ノ呼称ハ円トスル」と記されている。同時に補助通貨として「銭(1円の10分の1)」「厘(1銭の10分の1)」が定められた。明治政府はこの通貨決定に際し「10進法」、そして「国際通貨たること」に執拗以上のこだわりを示した。
周知の通り江戸時代の通貨は「両」を軸とした、「4進法」だった。「1両」「4分の1両:1分」「4分の1分:1朱」。4進法を「前近代の遺物」とし、何が何でも捨てなくてはならなかった。また10進法は日本を、ドルを先頭とする先進国通貨と肩を並べる国として位置付けるためにも不可欠だった。いかに「国際的国家」にこだわったかは、「1ドル・1円」の施策を講じたかにも顕著に見て取ることができる。「1円の価値は純金15gとする」という、金本位制を執ったのである。その背景は、当時の1ドル金貨の金の含有量が約15gだった点が指摘できる。
が、現実問題として1円:1ドルは早々に崩れていった。1894年(明治27年:日清戦争勃発)には1ドル:約2円という為替レートの記録が残っている。僅か20余年で円の対外価値は半減したのである。明治政府はこうした流れを受け、自虐的な措置を余儀なくされている。1円=純金1gを750mgと自らの手で円の価値を半減させたのである。ちなみに1917年(大正6年)に金本位制は廃止されているが、廃止当時まで円・ドル相場は1ドル・2円水準で推移している。だがそれでも円安の動きは止まらなかった。第2次世界大戦直前の実勢レートは1ドル:約4円まで下落している。
1円:1ドルが早々に崩れていったのも、当然の帰結だった。何故なら「続く貿易赤字:外貨を稼ぐための輸出品は極々限られていた。大幅な輸入超過が待ち構えていた。国際収支の赤字に連なる大幅な貿易赤字を避け得なかった」「政局不安定:下野した西郷隆盛率いる武族との西南戦争(1877年、明治10年)に象徴される内紛の続出により、軍事費負担の増加に見舞われた」。対応策は、円通貨の増発以外にない。明治時代は「インフレ」で幕を開けたのである。
ここまで引っ張っておいてそれはないだろう、という読者の声が聞こえてくる。円の歴史で今日なお解明されていない「二つの不思議」がある。一つは第2次大戦後に何故1ドル・360円が決められたのか。そしていま一つが「何故、日本の基軸通貨は円だったのか」。経緯については諸説あるが、公式文献の類いには、いきさつは一切残っていない。が、「通説」ではあるが限りなく「定説」に近いものとして語り継がれているのが、「円の名付け親は(早稲田大学の創始者でもある)大隈重信」論である。
明治政府が「新通貨」策定作業を進めている折りの、いまでいう財務大臣に当たる財務担当参謀である。こんな逸話が残っている。いわば経済・金融担当相会議の席上で大隈は、新基軸通貨の名称を「円にしよう」と提言した。キョトンとするお歴々を前に立ちがった大熊は(親)指と(人指し)指で円をつくり「これ、と示すと金の事を意味する。万国共通だ。そもそも通貨の多くが円(まる)い。新通貨の基本単位の呼び名は円(えん)で行こうじゃないか」と断定的に語ったというのである。(敬称、略)(記事:千葉明・記事一覧を見る)
スポンサードリンク
関連キーワード
スポンサードリンク
- 「日経平均が史上最高値を更新」という”幻想” 日銀も加担した「上げ底相場」という”現実” 4/ 9 15:33
- プライム上場企業に重要情報英文開示を義務化へ 4/ 7 20:32
- 2024年問題で住宅購入はどうなる? 今注目されるローコスト住宅ブランド
 4/ 7 20:32
4/ 7 20:32 - 経済効果は1607億円! オープン戦は最下位も、逆に「アレ」の期待が高まる?
 3/31 14:50
3/31 14:50 - 日本銀行が「デフレからの脱却」を目指して堕ちた罠 3/30 16:29