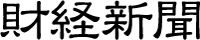関連記事
UMN Research Memo(2):研究開発ベンチャーから「バイオ医薬品製造」へ転進するためにアライアンス活動強化
*16:45JST UMN Research Memo(2):研究開発ベンチャーから「バイオ医薬品製造」へ転進するためにアライアンス活動強化
■会社概要
(1)会社沿革
a)苦難の創業時代
UMNファーマ<4585>はバイオベンチャーブーム花盛りの2004年4月に設立され、当初は大学発の医薬品候補シーズを開発すべく複数プロジェクト立ち上げ研究開発を進めていたが、研究開発から製品化へのいわゆる“魔の川(River Of Devil)”を越えられず、研究投資回収のめどが立たず、ついに2006年には研究プロジェクトを総入れ替えする苦い経験をしている。
また、社名の「UMNファーマ」はUnmet Medical Needs(有効な治療法や薬剤がない疾病領域における医療ニーズ)を満たす研究開発に全精力を注ぎたいとの創業者の強い思いから命名された。
b)独自の製造コアプラットフォーム「BEVS」との出会い
2006年8月に、米国PSC(Protein Sciences Corporation)と出会った。PSCはタンパク質の独自製造技術BEVS(バキュロウイルスによるタンパク質発現システムを用いたバイオ医薬品大量製造技術)を有するベンチャー企業で、当時いわゆるH5N1強毒性新型インフルエンザワクチンの開発に取り組んでいた。同社は革新的タンパク質製造技術BEVSの将来性を高く評価して、日本での次世代組換えインフルエンザワクチン独占開発製造販売契約のライセンス契約を締結した(後にアジア5ヶ国でのライセンス契約へ拡大)。
c)製造パートナーとの出会いによるワクチンの大規模製造バリューチェーンの確立
インフルエンザワクチンの事業化に際して、国内製薬メーカーとの提携推進には、インフルエンザワクチンの安定的大量供給体制の確立が必要条件であった。そこで、インフルエンザワクチンの原薬製造のパートナーとして、(株)IHI<7013>と共同研究を開始し、2010年には原薬製造に関して提携し、原薬製造子会社(株)UNIGENをJ/V(IHI50%、同社50%)で設立した。2013年5月には新ワクチン1,300~2,000万接種回分を供給(21,000L培養層2基時、最大8基まで増設可能)できる最新鋭バイオ医薬品の岐阜工場を竣工した。
また、各種健康食品などのOEM製造受託で有名なアピ(株)(岐阜県、年商約300億円、医薬品・健康食品の製造受託)と2010年、インフルエンザワクチンの製剤委託の業務・資本提携を締結した。
これにより、次世代インフルエンザワクチンの原薬~製剤まで大規模な製造バリューチェーンが確立し、新ワクチンの安定的大量供給体制が整った。
d)ワクチンの大手医薬品メーカーとの開発・販売提携
同社はインフルエンザワクチン市場への後発参入者として、当初はH5N1強毒性新型インフルエンザワクチンに注力した研究開発を進めていたが、2010年9月に季節性インフルエンザワクチンの国内トップシェアのアステラス製薬(株)<4503>との開発販売提携を契機に、既存市場である季節性インフルエンザワクチンへ研究開発をシフトしていった。また、2012年10月には韓国の日東製薬(株)と販売提携に基本合意し、韓国市場でのインフルエンザワクチンの開発販売の準備が整った。
(2)会社の特徴と役割
バイオ創薬ベンチャーは知財ライセンス収入が一般的であるが、同社は自社で研究開発したバイオ医薬品(新ワクチン)の製造まで取り組む数少ないベンチャー企業である。国内では、インフルエンザワクチンの大量供給体制を整えてから事業化した希有なベンチャー企業である。
また、国では新型インフルエンザなどによる感染症リスクから国民の生命と健康を守らなければならない。パンデミックが発生した場合、政府や医療機関は、食糧備蓄と同様にワクチンを国家戦略物資として、数千万人規模の感染症ワクチンを迅速に確保しなければならない。同社の子会社(株)UNIGENの岐阜工場では、培養槽を増設することで最大8千万人分のワクチン生産能力を有する。ワクチン製造の国内生産としての重要な役割を担っており、日本の国家戦略物資の生産拠点としてなくてはならない企業である。
(3)事業概要
a)安定的大量生産プラットフォームをベースに組換え型ワクチンの開発~原薬製造まで一気通貫事業体制
同社は、次世代組換え型ワクチンの安定的大量生産プラットフォーム(BEVS)をベースに、自社開発品ワクチン(季節性インフルエンザや次世代ノロウイルスワクチンなど)供給の事業化を目指しており、さらに、バイオ医薬品原薬供給(バイオシミラー“後続品”)事業も実践化段階にある。
自社開発品の次世代インフルエンザワクチンは「遺伝子組換え技術」を用いたワクチン製法を利用しており、顧客メリットも多く、製造販売が認可されれば、従来ワクチン製法(孵化鶏卵法)による既存ワクチンの代替化が急速に進むと予想される。さらに、ノロウイルスやジカウイルス向け次世代ワクチンが開発に成功すれば、世界初のワクチンとなり、市場創造で先行者利益の獲得も現実のものとなる。
一方、バイオ医薬品原薬供給事業は、一定レベル以上の科学技術と、労働集約的な開発、大資本を必要とする製造設備投資、そしてリスクに対して迅速に決断できる社内体制など、半導体やスマートフォンで培ったビジネス感覚が必要で、ロンザ(スイス)、べーリンガーインゲルハイム(ドイツ)を始め、韓国勢(セルトリオン、サムスンバイオエピス)などが参入するコスト競争(レッドオーシャン)市場であり、同社は厳しい戦いの覚悟が必要となる。
b)次世代バイオ医薬品生産プラットフォームBEVSの特徴と優位性
BEVS(Baculovirus Expression Vector System)は2006年に米国PSCから技術導入したバイオ医薬品の生産プラットフォームで、ワクチン大量生産の“心臓部”に当たる。
BEVSは従来のワクチン製造法とどこが異なるのか検討してみた。インフルエンザワクチンの原理は、インフルエンザウイルスが細胞内に侵入する際に必要なタンパク質成分をHA(ヘマグルチニン)と言うが、そのHAをワクチン成分として接種することによりヒトの免疫に記憶させ、本体ウイルスが侵入してきた時に免疫が賦活化されて作られた抗体で感染を防御する。
インフルエンザウイルスは、本来鳥に感染するウイルスであるが、ヒトに感染するようにウイルスの遺伝子構造が変異している。ヒトに接種したワクチンの有効性を最大化にするには、ヒトで流行しているインフルエンザウイルスの遺伝子タイプと一致するHA(ワクチン成分)を接種する必要がある。しかし、従来の孵化鶏卵法では、孵化鶏卵で増殖させるために、鳥型ウイルス対応のワクチンに逆戻り(先祖返り)して、特に、一部インフルエンザウイルスには免疫効力を発揮しないケースが多発している。また、他のワクチンメーカー等で開発が進められている単純細胞培養法も、培養過程に哺乳動物の細胞を使用するため、製造過程において孵化鶏卵法同様に変異が起こり、一部インフルエンザウイルスに免疫効力が発揮できない可能性があることが報告されている。
ノロウイルスは、ヒトの中でのみ増殖するため、孵化鶏卵法など従来のワクチン製造方法ではワクチン成分の製造は困難であったが、BEVSの遺伝子組換え技術を利用することで大量に製造することが可能なことから実用化に向けての研究が進んでいる。
また、製造安定性面でも、BEVSは他の製法に比べて優位性があるようだ。その理由は、培養に使う細胞のストレス耐性の違いにある。〔A〕は孵化鶏卵細胞、〔B〕は動物細胞に対して、〔C〕は昆虫細胞であるため、大量培養プロセスにおいてもストレスに強いことから培養効率が低下せず、培養基をスケールアップしても収率ダウンしないメリットがある。
(4)季節性インフルエンザワクチンの日本・米国市場規模推移
a)当面の参入市場である季節性インフルエンザワクチン市場(日本、米国)は高成長が持続
季節性インフルエンザワクチン国内市場は、2000年以降拡大傾向にあり、現在は約6,000万接種回分のワクチン需要があり、国民の約2人に1人分が生産されている。また、現在、2015−2016年シーズンより3価から4価への移行に伴い、販売価格は1.5倍となり、金額ベースでは大きく市場拡大している。ちなみに、予防ワクチンは薬価制度対象外であり、薬価引き下げリスクやジェネリックへの置換リスクの影響は受けない。
一方、季節性インフルエンザワクチンの米国市場は、数量ベースで1.7億接種回分と日本市場の2.85倍、金額ベースでは3倍以上、今後も成長は続くと見られる。現在はほとんどが孵化鶏卵法による既存ワクチンであるが、PSCが実施した発症予防効果臨床試験で、既存ワクチンに対して統計的有意差をもってインフルエンザ発症例数が少なかったことが示され、今後、同社の組換え型ワクチンへの切り替えが進むことが予想される。
(執筆:フィスコ客員アナリスト 清水 啓司)《HN》
スポンサードリンク
スポンサードリンク